理事長:川村千鶴子 Chief Director: Emer. Prof. Dr. KAWAMURA Chizuko

大東文化大学名誉教授。博士(学術、総合研究大学院大学)。東アジア経営学会国際連合産業部会、NPO法人太平洋協力機構顧問。
略歴:慶應義塾大学卒、多文化教育研究所長、大東文化大学環境創造学部教授、同学部長。移民政策学会理事、日本オーラル・スストリー学会理事、日本島嶼学会理事、法務省調査検討委員会有識者会議委員、難民支援協会スペシャル・サポーター、2021年経済産業省中小企業庁委託『企業におけるCSR/人権担当者向け実践講座』の講師を担当。2022年第6回「外国人雇用の道を拓く-人権尊重の共創経営の知恵」講師担当(公財:人権教育啓発推進センター)を歴任。
主な書籍『多文化都市・新宿の創造』(慶應義塾大学出版会2015単著)。主な編著書『多民族共生の街・新宿の底力』(明石書店1998)『多文化教育を拓く』(明石書店2002)、『異文化間介護と多文化共生』(明石書店2007)。『移民政策へのアプローチ』(明石書店2009)、『「移民国家日本」と多文化共生論』(明石書店2008)、『3.11後の多文化家族』(明石書店2012)、『移動する人々と日本社会』(ナカニシヤ出版2013)、『多文化社会の教育課題』(明石書店2014)、『多文化「共創」社会入門』2016、『いのちに国境はない』(慶應義塾大学出版会2017)。『多文化共創社会への33の提言ー気づき愛 Global Awareness』(編集代表、都政新報社2021)、共著に『外国人労働者問題と多文化教育』(明石書店)、『日本の移民政策を考える』(明石書店2005)、『オセアニア学』(京都大学学術出版会2009)、『人の移動事典』(丸善出版2013)、『パスポート学』(北海道大学出版会2017)、『インタラクティブゼミナール 新しい多文化社会論―共に拓く共創・協働の時代』(共編著、東海大学出版部2020)、『多文化社会の社会教育―公民館・図書館・博物館がつくる「安心の居場所」』(明石書店2019)、他多数
副理事長:渡辺幸倫 Vice-Chief Director: Prof. WATANABE Yukinori

相模女子大学教授。早稲田大学大学院教育学研究科博士後期課程単位取得退学。大東文化大学非常勤講師、立教大学兼任講師などを経て、現職。専門は多文化教育、言語教育。
主な業績に、『博物館がつくる「安心の居場所」』(編著、明石書店、2019年)、『買い物弱者とネット通販 在外子育て家庭からの示唆』(共編著、くんぷる、2019年)、『多文化「共創」社会入門 移民・難民とともに暮らし、互いに学ぶ社会へ』(共著、慶應義塾大学出版会、2016 年)、『多文化社会の教育課題 : 学びの多様性と学習権の保障』(共著、明石書店、2014 年)など
副理事長:明石純一 Vice-Chief Director: Prof. Dr. AKASHI Junichi

博士(国際政治経済学)。筑波大学人文社会系教授。移民政策学会事務局長、公益財団法人アジア福祉教育財団理事、一般財団法人日伯経済文化協会評議員。専門は国際政治経済学、移民研究。法務省・難民審査参与員(2015年~現在)、法務省・第七次出入国管理政策懇談会委員(2016年~2019年)、内閣官房・第三国定住による難民の受入れ事業の対象拡大等に係る検討会有識者メンバー(2018年~2019年)、法務省・収容・送還に関する専門部会委員(2019年~2020年)、内閣官房・教育未来創成会議有識者メンバー(2022年~2023年)など。
主要業績に、『入国管理政策:「1990体制」の成立と展開』(ナカニシヤ出版、2010年、単著)、『移住労働と世界的経済危機』(明石書店、2011年、編著)、『グローバル人材をめぐる政策と現実』(明石書店、2015年、共編著)。『変容する国際移住のリアリティ:「編入モード」の社会学』 (ハーベスト社、2017年、共編著)、『人の国際移動は管理されうるのか:移民をめぐる秩序形成とガバナンス構築』(ミネルヴァ書房、2020年、単著)、Migration Policiesin Asia(Sage、2020、共編著)、『移住労働とディアスポラ政策:国境を越える人の移動をめぐる送出国のパースペクティブ』(2022年、筑波大学出版会、編著)など。
副理事長:李錦純 Vice-Chief Director: Prof. Dr. Lee Kumsun, RN, PHN

関西医科大学看護学部・看護学研究科教授。博士(人間科学)、修士(看護学)。看護師、保健師、介護支援専門員。
専門は在宅看護学、国際看護学、高齢者看護学。大学病院および訪問看護ステーション等で臨床経験を経て、2010年~近大姫路大学(現:姫路大学)専任講師・准教授、2013年~兵庫県立大学看護学部准教授、2018年~現職。2011年~姫路市人権啓発センター運営推進会議委員、2016年~国際地域看護研究会代表(2022~会員)。2018年~関西医科大学看護学部・看護学研究科准教授、2022年~現職。
多様な背景をもつ人々が、地域社会で安心して豊かな老後を過ごせるような多文化共生・共創社会を目指して、大学、行政、市民団体、研究会などで広く教育・研究・社会貢献活動に携わっている。
主な業績は、『在日外国人の高齢者保健福祉に関する研究』(単著、風間書房, 2020年)、『多文化共創社会への33の提言―気づき愛Global Awareness』(共編者、都政新報社、2021年)、『在日外国人の健康支援と医療通訳―誰一人取り残さないために―』(共著、杏林書院、2018年)、『多文化社会の看護と保健医療―グローバル化する看護・保健のための人材育成』(共訳、福村出版、2015)など。
副理事長:増田隆一 Vice-Chief Director: Mr. MASUDA Ryuichi

1978年京都大学工学部卒業。朝日放送株式会社入社後、1987年~1991年ANNパリ特派員「ベルリンの壁崩壊」「ルーマニア革命」「湾岸戦争」などを取材・送稿。インターネット事業部長・メディア戦略部長として「テレビのデジタル化」の政府調整を担当。AM・FMラジオのPC・スマホ経由聴取アプリ「radiko」事業を創設したメンバーの一人。
2017年公益財団法人地球環境戦略研究機関にコミュニケーション・ディレクターとして入所。国際シンポジウム「ISAP2017」の運営責任者。UNFCCCのCOP23(ドイツ・ボン)における日本政府「日本パビリオン」の運営事務局。
著書:『変わりゆくマスメディア』(単著、あみのさん、2016年)『いのちに国境はない』(共著、慶應義塾大学出版会、2017年)
専務理事兼事務局長:万城目正雄 Prof. MANJOME Masao

東海大学教養学部人間環境学科教授。専門:国際経済学
国際研修協力機構に20年の勤務を経て、2016年4月より東海大学に移り、教養学部人間環境学科で教鞭をとる。専門は国際経済学。
アセアン諸国との送出国政府との実務者協議に多数参加。外国人を送り出すアジア諸国の事情と日本の中小企業、農家、外国人材、技能実習制度、特定技能制度に詳しい。技能実習機構・産業人材育成機構の検討委員会委員。経緯は『望星10月号』(東海教育研究所2019年)などでも紹介される。
主な著作に『移民・外国人と日本社会』(共著、原書房、2019)、『工場管理―総論』(共著、日刊工業新聞社、2019)、『プレス技術―総論』(共著、日刊工業新聞社2019)、『インタラクティブゼミナール 新しい多文化社会論―共に拓く共創・協働の時代』(共編著、東海大学出版部2020)ほか多数。
理事:
明石留美子 Prof. Dr. AKASHI Rumiko

明治学院大学 社会学部 社会福祉学科 教授。 Ph.D. (社会福祉学)
専門は社会福祉学、ジェロントロジー、国際福祉学
UNICEFモンロビア事務所 (リベリア)、UNICEF西・中央アフリカ地域事務所 (コートジボワール)、国際協力機構(フィリピン貧困緩和プロジェクト担当)、世界銀行東京事務所での勤務を経て、明治学院大学社会学部社会福祉学科准教授に就き、現職に至る。
10年間、開発援助に従事し、米国ニューヨーク州のコロンビア大学スクール・オブ・ソーシャルワークに留学して理学修士号、哲学修士号、Ph.D.を取得。
2017-18年、カリフォルニア大学バークレー校スクール・オブ・ソーシャルウェルフェアの客員研究員としてジェロントロジー研究に従事。
国際に関わる主要業績として、『地域づくりの福祉援助』(ミネルヴァ書房、共著、2006)、『世界の社会福祉年鑑2010』(旬報社、共著、2010)、『新 世界の社会福祉』(旬報社、共著、2020)。国際研究の主要論文として、「ミレニアム開発目標とソーシャルワーク実践−開発途上国への国際協力における国際社会福祉の役割についての考察」(『ソーシャルワーク研究』 36巻3号、2010)、「国際福祉開発フィールドワークの学習効果を学生はどのように認識するのか-国際サービスラーニングの視点から学生の学習認識を評価する」(『明治学院大学社会学・社会福祉学研究』 143巻、2014)など。
秋山肇 Prof. Dr. AKIYAMA Hajime
筑波大学人文社会系助教、博士(学術)
阿部治子 Ms. ABE Haruko
自治体職員。図書館の多文化サービスや生活保護行政、自治・協働推進施策、多文化共生推進施策などに携わる。
現在、公益社団法人 日本図書館協会「多文化サービス委員会」副委員長、「むすびめの会」(図書館と多様な文化・言語的背景をもつ人々をむすぶ会)事務局、「夜間中学校と教育を語る会」事務局、「多文化社会研究会」事務局など。主な業績に、『図書館の達人〈司書実務編8〉新しい文化の創造をめざして(VHS)』(制作協力、紀伊国屋書店、1999年)、『多文化サービス入門(JLA図書館実践シリーズ2)』(共著、日本図書館協会多文化サービス研究委員会編;日本図書館協会、2004年)、『多文化サービス実態調査2015年報告書』(共著、日本図書館協会多文化サービス委員会編;日本図書館協会、2017年)、『多文化社会の社会教育―公民館・図書館・博物館がつくる「安心の居場所」』(共著、明石書店、2019年)など。
荒井幸康 Prof. Dr.ARAI Yukiyasu
北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター共同研究員、公益社団法人日本モンゴル協会理事。亜細亜大学、芝浦工業大学、青山学院大学、東京女子大学、一橋大学、東京大学非常勤講師。一橋大学言語社会研究科修了、博士(学術)。
専門はモンゴル学、社会言語学(言語の社会史、言語政策、ソビエト言語学論、リテラシー、翻訳論)。元帰国子女。
主な業績に『「言語」の統合と分離―1920‐1940年代のモンゴル・ブリヤート・カルムイクの言語政策の相関関係を中心に』(単著、三元社、2006)、「モンゴル諸民族、ソヴィエト初期言語政策に見る文字と政治」(単著、『ことばと文字』、2015)、『聖書翻訳を通してみるモンゴル -東北アジア宗教文化交流史の文脈から-』(共著、東北アジア研究センター、2017)など
五十嵐 ゆかり Prof. Dr. IGARASHI Yukari, RN, CNM

聖路加国際大学大学院看護学研究科教授。博士(看護学)。専門は、ウィメンズヘルス・助産学、異文化看護学。助産師。RASC代表。
2006年に多文化医療サービス研究会(RASC)を立ち上げ、日本で出産・育児をする外国人女性とその家族のサポートを行っている。主な出版は『国際化と看護 (3.地域における在留外国人の支援の実際)』(MCメディカ出版、2018年)『パーフェクト臨床実習ガイド 母性看護 第2版 (ケーススタディ 外国人妊産婦への援助)』(照林社、2017年)、『多文化「共創」社会入門(第2章多文化と医療)』(慶応義塾大学出版会、2016年)、『母性看護学Ⅰ概論(第3章 第3節 在日外国人の母子保健)』(医歯薬出版、2015年)など。
伊藤寛了 Prof.Dr. ITO Hiroaki
帝京大学経済学部専任講師。博士(学術)。2001年東京外国語大学卒業。2010年同大学院博士後期課程修了。その間、トルコ共和国アンカラ大学(学部)およびボアズィチ大学アタテュクル研究所(大学院)に留学。在トルコ日本国大使館専門調査員(2006-2008)、アジア福祉教育財団難民事業本部(2009-2019)などを経て、2019年より現職。
主な業績に「トルコにおけるシリア難民の受け入れ−−庇護、定住・帰化、帰還をめぐる難民政策の特質と課題」小泉康一(編)『「難民」をどう捉えるか−−難民・強制移動研究の理論と方法』(慶應義塾大学出版会、2019)、「日本における難民受け入れと定住支援の歩み」(『国連ジャーナル』2019年春号、2019年)、第三国定住によるミャンマー難民の受け入れとは?」滝澤三郎(編)『世界の難民をたすける30の方法』(合同出版、2018年)、「ポスト・アタテュルク時代のイスラム派知識人」新井政美(編)『イスラムと近代化:共和国トルコの苦闘』(講談社選書メチエ、2013)、「イノニュの時代のトルコにおけるラーイクリキ議論の展開」粕谷元(編)『トルコ共和国とラーイクリキ』(上智大学イスラーム地域研究機構、2011年)、「近年のトルコにおける世俗派とイスラーム派の対立とトルコ民族主義の高揚」(『イスラム世界』72号、2009年)、「オスマン帝国末期におけるズィヤー・ギョカルプのナショナリズムとイスラーム改革思想」(『イスラム世界』65号、2005年)など。
井口博充 Prof. Dr. INOKUCHI Hiromitsu
ウィスコンシン大学マジソン校でPh.D.を取得(1997年)、日本の大学で教えた後、ニューヨーク州立大学バッファロー校客員教授(〜2012年)。現在、大東文化大学、専修大学非常勤講師、アムネスティ・インターナショナル日本理事(2019年〜)。
専門は、教育社会学、コミュニケーションの社会学、言説研究、人種・民族マイノリティ(とりわけ、在日コリアン、アジア系アメリカ人)や他者の問題など。近年は、国際人権法にも強い関心をもつ。
主な著書に、『情報・メディア・教育の社会学:カルチュラル・スタディーズしてみませんか?』、What U.S. Middle School Students Bring to Global Education: Discourses on Japan, Formation of American Identities, and the Sociology of Knowledge and Curriculumなどがある。
大野勝也 Mr. OHNO Katsuya

AFP。不動産業従事。日本大学大学院文学研究科社会学専攻博士前期課程修了。修士(社会学)。専門は社会学、都市社会学、住宅問題、ハウジング論。修士論文では、ハウジング研究の変遷を踏まえ、国内における住宅政策の過程における日本型住宅供給システムの諸相を考察した。実務では、不動産管理業務を行い、様々なアクターとの関わりを踏まえた研究活動を行っている。研究領域は、民間賃貸住宅を中心とした市場と管理実践の場における諸課題において、維持管理を行う家主・不動産業研究。多文化社会研究会理事、多文化研ユース代表。
【主な業績等】
「日本における零細家主形成のプロセスと課題-外国人に対する住宅供給時の葛藤をめぐって―」(『ソシオロジクス』42号、2020年)、活動実績として、日本大学大学院社会学研究会一同、「コロナ禍における大学院の活動記録」(『ソシオロジクス』43号、2021年)、口頭発表:第164回多文化共創フォーラム「経済学の視点から移民政策を考える」 第2回:コロナ禍で変わる居住・住まい方と不動産業界「住宅政策から考える安心の居場所~零細家主と民間賃貸住宅における外国人住宅供給~」(多文化社会研究会2020年8月)。
大山彩子 Dr. OYAMA Ayako

お茶の水女子大学大学院修士(社会科学)。英国アングリアラスキン大学大学院にてPh.D.取得。博士論文では、東京都新宿区とロンドン・ニューアム地区の多文化共生の実践者たちにインタビューを行い、彼らからみた多文化共生の形を分析し比較した。新宿とニューアムには歴史的、人口構成的、政策的な違いがあり、地域の特徴に合わせた実践があるものの、首都の中で最も多様な人口構成を持っている両地区の実践者たちの多文化共生への思いには共通点が多いことを明らかにした。
専門は、社会統合(Integration)、多文化共生・多文化共創、移民政策、国際福祉。
英国在住18年。現在はOxfamでボランティア活動中。
加藤丈太郎 Prof. Dr. KATO Jotaro

武庫川女子大学文学部英語文化学科専任講師。博士(学術)。
大学時代、ロンドンで黒人家庭にホームステイしたことをきっかけに人種差別・移民/難民問題の解決に関心を持つ。NGOにて非正規滞在者(ビザを持たない外国人)の在留資格取得の支援に携わった後、現所属に。専門は移民研究、国際労働移動、国際社会学。非正規滞移民、移民と難民の混在移動、移民政策に関心を有する。日本でその人口を急増させているベトナム人とフィールドで関わりながら研究を続けている。
専門:移民研究、国際労働移動、国際社会学。
論文に「『不法性』と共に生きる―非正規滞在者が日本で暮らすことを可能とする要因は何か―」移民政策研究』11号)、‘Migration infrastructures and the production of migrants’ irregularity in Japan and the United Kingdom.’ Comparative Migration Studies 9(31). (Co-author: Sigona, Nando and Irina Kuznetsova)、
著書:共著『多文化共生 人が変わる 社会を変える』(共著、凡人社、2018年)、単著『日本の「非正規移民」-「不法性」はいかにつくられ、維持されるかー』(明石書店、2022年3月)などがある。
小林真生 Prof. Dr. KOBAYASHI Masao
立教大学兼任講師。早稲田大学大学院アジア太平洋研究科博士後期課程修了。博士(学術。早稲田大学)編著『変容する移民コミュニティ』(駒井洋監修、明石書店、2020年)
群馬県太田市出身。学生の頃より、周囲に外国人労働者(パキスタン人、日系ブラジル人など)が増加する状況を体感する一方、地元企業(三洋電機、現パナソニック)のラグビー部でプレーするトンガ人プレーヤーを応援。同志社大学法学部政治学科を経て、早稲田大学大学院アジア太平洋研究科で学び、社会学の観点から「日本社会における対外国人意識」「海外出身のラグビー選手の状況や国籍認識」を研究。同大学院にて博士(学術)を取得。
単著として『日本の地域社会における対外国人意識-北海道稚内市と富山県旧新湊市を事例として』福村出版、2012年。編著として『移民・ディアスポラ研究3-レイシズムと外国人嫌悪』明石書店、2013年。論文として、「対外国人意識改善に向けた行政施策の課題」『社会学評論』第58巻第2号、2007年など。
ラグビー関連の著作として、「多文化共生に向けた環境整備の重要性―トンガ人ラグビー選手の事例から」『環境創造』第13号、2010年。「日本代表として闘う-日本国籍を取得した外国人ラグビー選手たち」佐々木てる編『移民ディアスポラ研究5-マルチ・エスニック・ジャパニーズ:○○系日本人の変革力』明石書店、2016年など。
佐伯康考 Prof. Dr. SAEKI Yasutaka

公立大学法人 静岡文化芸術大学文化政策学部 国際文化学科 准教授。博士(経済学)。外国人労働者を中心とした国際的な人の移動について研究を行っている。著書に『国際的な人の移動の経済学』(明石書店2019), 共編著に『街に拓く大学―大阪大学の社学共創―』(大阪大学出版会, 2019),『グローバルな公共倫理とソーシャル・イノベーション』(金子書房, 2018)がある。多文化社会研究会理事、移民政策学会国際交流委員・社会連携委員。
佐々木てる Prof. Dr. SASAKI Teru

青森公立大学 経営経済学部 地域みらい学科 教授。博士(社会学)。
略歴:東洋大学社会学部卒業。筑波大学社会科学研究科社会学専攻修了。筑波大学助手、青森大学社会学部教授を経て現在に至る。
所属学会:日本社会学会、移民政策学会、オーラルヒストリー学会。
専門:国際社会学、地域社会論。博士論文では在日コリアンの帰化をテーマに執筆。現在は重国籍(複数国籍)に関する研究をすすめている。また青森では、地域社会を研究対象とし、地元の祭(ねぶた祭)を通じた地域住民のネットワークについて分析。また青森県の人口減少対策としての外国人住民の移住・労働に関しする研究を行っている。
主な業績:『日本の国籍制度とコリア系日本人』(単著、明石書店2006)、『マルチ・エスニック・ジャパニーズ:〇〇系日本人の変革力』(編著、明石書店2016)。『パスポート学』(編著、2016北海道大学出版会)、「日本人にはなれない、日本人であり続けることができない」『別冊環 24』(藤原書店2019)、「複数国籍容認にむけて―現代日本における重国籍者へのバッシングの社会的背景」『移民政策研究11』(移民政策学会2019)、「保守化する時代と重国籍制度 ~ナショナル・アイデンティティから視る現代日本社会の国籍観~」『エトランデュエ』(在日本法律家協会2018)など多数。(詳細はこちら:https://researchmap.jp/terurio/)
下川進 Mr. SHIMOKAWA Susumu
杉田昌平 Mr. SUGITA Shohei

2007年慶應義塾大学法学部法律学科卒業、2010年慶應義塾大学大学院法務研究科修了、2011年最高裁判所司法研修所修了し、2011年から東京弁護士会に弁護士として登録しています。
2011年から2015年までセンチュリー法律事務所、2015年から2017年まで、アンダーソン・毛利・友常法律事務所及び名古屋大学大学院法学研究科日本法教育研究センター(ベトナム)にて勤務しておりました。
2017年にベトナムから帰国してからは、センチュリー法律事務所に戻り、また、慶應義塾大学大学院法務研究科の特任講師として執務しました。その後、弁護士業としては2021年6月に弁護士法人Global HR Strategyの代表弁護士として独立し、慶應義塾大学大学院法務研究科の特任講師は2021年3月に退任し、翌月の2021年4月から独立行政法人国際協力機構国際協力専門員(外国人雇用/労働関係法令及び出入国管理関係法令)として勤務しております。
現職は、弁護士法人Global HR Strategy・代表社員、社会保険労務士事務所Global HR Strategy代表、独立行政法人国際協力機構国際協力専門員(外国人雇用/労働関係法令及び出入国管理関係法令)、慶應義塾大学大学院法務研究科・グローバル法研究所研究員を務めております。
書籍としては実務書が多く『中国・タイ・ベトナム労働法の実務Q&A』(労働調査会、2018)(共著)、『改正入管法対応 外国人材受入れガイドブック』(ぎょうせい、2019)、『改正入管法関連完全対応 法務・労務のプロのための 外国人雇用実務ポイント』(ぎょうせい、2019)、 『「技能実習」「特定技能」対応!!外国人材受入れサポートブック』(ぎょうせい、2020)、『外国人材の雇用戦略 ~採用・法務・労務』(日本法令、2020)(共著)、『外国人高度人材はこうして獲得する!―「準備」「手続」「定着」の採用戦略―』(ぎょうせい、2020)(共著)、『外国人住民の生活相談Q&A~子育て・教育から医療・福祉まで~』(ぎょうせい、2020)(共著)等を執筆しています。
関口明子 Ms. SEKIGUCHI Akiko

現職:公益社団法人国際日本語普及協会(AJALT)理事
1982年社団法人(現公益社団法人)国際日本語普及協会(AJALT)に入会し、同会理事長職(2014~2022)、会長職(2022∼2024)を経て、現在に至る。兼職として1982年~1998年 (財)アジア福祉教育財団難民事業本部大和定住促進センターにおいてインドシナ難民年少者および成人への日本語教育に従事。(1990~1998年主任講師)。1995年~2009年横浜国立大学教育人間科学部講師。
主な外部役職
・公益財団法人日本国際教育支援協会 日本語教育能力検定試験実施委員会委員
・公益社団法人日本語教育学会 監事・公益財団法人海外日系人協会評議員
・公益財団法人アジア福祉教育財団難民事業本部日本語教育参与
・一般財団法人言語教育振興財団評議員
・公益財団法人日本テレビ小鳩文化事業団評議員
・農林水産省飲食料品製造業試験策定委員
・文化庁日本語教室空白地域解消推進事業日本語教育シニアアドバイザー
主な論文・書籍
・「日本定住児童の日本語教育・インドシナ難民児童の多様な言語背景と日本語教育」『日本語教育83号』
・『かんじだいすき』シリーズ(一)~(六)および社会・理科編/国語・算数編、練習帳(共著)(公社)国際日本語普及協会
・『多言語社会と外国人の学習支援』(共著)慶応義塾大学出版会
・『命に国境はない~多文化「共創」の実践者たち』(共著) 慶應義塾出版会
・『じっせんにほんごー技術研修編』『あたらしいじっせんにほんごー技能実習編』『あたらしいじっせんにほんご2-働く日本語学習者のために』(共著)(公社)国際日本語普及協会・『新版日本語教育辞典』(共著)大修館書店。他
関本保孝 Mr. SEKIMOTO Yasutaka
《経歴》1978年より東京都内夜間中学日本語学級で日本語指導(約36年)。2014年3月定年退職。
《現職・所属》
・多文化社会研究会理事・基礎教育保障学会事務局長/・東京の日本語教育を考える会事務局長
・えんぴつの会・ボランティア/・ピナット子ども学習支援教室コーディネーター
・夜間中学校校と教育を語る会事務局員/・神奈川・横浜の夜間中学を考える会事務局員
《主な論文等》
・『外国人・民族的マイノリティー人権白書2018』(2018年3月外国人人権法連絡会)第6章マイノリティの子どもたちの権利「夜間中学」
・『いのちに国境はない~多文化共創の実践者たち』(2017年2月慶應義塾大学出版会)「第6章 夜間中学でいつでも誰でもどこでも基礎教育を!」
・『社会的困難を生きる若者と学習支援~リテラシーを育む基礎教育の保障に向けて~(2016年8月 明石書店) 「第3章 公立夜間中学校(東京都)」
・『月刊社会教育2017年4月号』(国土社)「『義務教育機会確保法』の成立と国・自治体・民間団体の課題」
・『月刊社会教育』2015年4月号 シリーズ夜間中学1「夜間中学で学ぶということ」
・『月刊社会教育』2014年10月号「夜間中学の現状と役割、そして未来へ」
・『教育』(1998年10月号 国土社)「東京・夜間中学校―夜間中学校の現場から」( 特集 グローバル化と在日の子どもたち 共生の空間 )その他。
芹澤健介 Mr.SERIZAWA Kensuke

作家。ノンフィクション・ライター。1973年、建設省(当時)の技官であった父の仕事の関係で、沖縄県那覇市で出生。5歳からは、茨城県つくば市で育つ。高校は土浦第一高等学校(本館が古く、大正・昭和初期あたりが舞台のドラマでよく使われます)。
1992年、高校卒業後に一浪し、なんとなく東大を目指していたものの、実力通りの結果しか出せず、横浜国立大学経済学部国際経済学科に入学。95〜96年にかけて休学。海外放浪。ゼミは華僑経済史が専門の飯島渉ゼミに所属。卒論のテーマは「戦前の横浜における移民宿の実態〜沖縄移民との関係を中心に〜」。この年の経済学部の優秀賞をいただき、結果的に物書きの道へ。
98年より都内の編集プロダクションで修業、30歳で独立、現職(フリーライター)。30代のうちは純文学への志向も強く、講談社の群像新人賞の最終候補になったこともありましたが、徐々にフィクションからノンフィクションの方向へ。
多文化研に入会させていただいたのは『コンビニ外国人』という拙著がきっかけですが、最近は「日本文化の海外への伝播と交流」みたいなことに興味もあり、簡単に言うと、日本の代表的な食文化である寿司とその周囲の人間ドラマ(『世界寿司歩き』(仮))という本が書けないだろうかと妄想しながら、寿司と外国人にまつわるネタを集めている日々です。仕事をする以外は、料理をしたり(家では私が料理担当。洗濯は妻担当)、猫とかまけています。
【主な業績等】
2014年、沖縄の青年軍医の半生を描いた小説『血と水の一滴』(丸善出版)上梓。
2015年より、NHK worldの番組制作(「great gear」2020休止)にも携わるようになる。
2018年、『コンビニ外国人』(新潮新書)2018年5月 上梓。
2019年、『となりの外国人』(マイナビ新書)2019年12月 上梓。
2022年、第5のがん治療法とも呼ばれる光免疫療法についてのドキュメンタリー『がんの消滅 〜天才医師が挑む光免疫療法』(新潮新書)2023年8月 上梓。
チョウ・チョウ・ソー Mr. Kyaw Kyaw Soe

1984年ヤンゴン経済大学卒業。
民主化運動に参加。1991年軍事政権の弾圧を逃がれて日本に亡命。難民申請から数年後、1998年に難民と認定された。妻ヌエ・ヌエを呼び寄せる。髙田馬場でビルマ料理店「ルビー」を経営。東日本大震災では被災者支援に赴いた。
NHK国際放送「ラジオ日本」ビルマ語アナウンサー。
母語保持教育を主宰。ジャーナリスト、教育者として活躍している。共著多数。
土田千愛 Dr. TSUCHIDA Chiaki
東京大学地域未来社会連携研究機構特任助教。博士(国際貢献)。
専門は、国際関係論、移民・難民研究。
第2回若手難民研究者奨励賞受賞(2014年)。第4回東京大学而立賞受賞(2023年)。
主な業績に、『日本の難民保護—出入国管理政策の戦後史』(単著、慶應義塾大学出版会、2024年)、「難民条約加入前の難民保護に対する日本政府のアイディアの変容—難民保護に関する政治過程の分析より」(『移民政策研究』、第12号、2020年)、『多文化社会の社会教育—公民館・図書館・博物館がつくる「安心の居場所」』(共著、明石書店、2019年)、『いのちに国境はない—多文化「共創」の実践者たち』(共著、慶應義塾大学出版会、2017年)など。
長谷川礼 Prof.HASEGAWA Rei

大東文化大学経営学部教授および同大経営研究所所長。同大学キャリアセンター長、経営学部長、Proctor & Gamble在日子会社(現P&Gジャパン)勤務を経て現職。早稲田大学商学研究科博士後期課程単位取得退学。American Graduate School of International Management国際経営学修士。専門は国際経営。
主要業績:「女性労働者の離職意向に関する職位・企業タイプ別比較分析」『経営論集 長島芳枝教授追悼号』第42・43合併号大東文化大学経営学会(2022)、“The Inferred Determinants of Employees’ Turnover Intentions: A Comparison between Japanese and Foreign-owned Firms in Japan”, International Journal of Business and Management Vol. 16, No. 8 published by the Canadian Center of Science and Education(共著:Rei Hasegawa, Shinji Hasegawa & Takashi Akiyama)(2021)、「高齢労働者の就労意欲等に関する分析」大東文化大学経営研究所編『ダイバーシティ・マネジメントに関する多角的研究』大東文化大学経営研究所経営叢書38(2020)、「P&Gと花王におけるブランドマネジメント制」『国際ビジネス研究学会年報』第8号 国際ビジネス研究学会編(2002)
人見康弘 Prof. Dr. HITOMI Yasuhiro
武蔵大学社会学部准教授。博士(文学)。
専門は国際社会学、移民・難民研究。
主な業績として『難民問題と人権理念の危機―国民国家体制の矛盾』(編著、2017年、明石書店)のほかに、移民政策学会設立10周年記念論集刊行委員会編『移民政策のフロンティア―日本の歩みと課題を問い直す(「戦後日本の難民政策―受入れの多様化とその功罪」)』(2018年、明石書店)、滝澤三郎・山田満編『難民を知るための基礎知識―政治と人権の葛藤を越えて(「第四部 難民の社会統合」)』(2017年、明石書店)、西原和久・樽本英樹編『現代人の国際社会学・入門―トランスナショナリズムという視点(「第七章 ASEANのトランスナショナリズム」)』(2016年、有斐閣)など。
藤波香織 Ms. FUJINAMI Kaori

現職:埼玉県庁勤務
経歴:埼玉県庁入庁後、多文化共生、グローバル人材育成、官民連携支援、保健医療福祉、議会事務局等に従事。2010年政策研究大学院大学修了(政策研究修士)。2018 ~2020年度(一財)自治体国際化協会(クレア)派遣(多文化共生課長)。県国際課では多言語相談窓口運営、子ども支援・多文化ソーシャルワーク調査研究、外国人住民の地域参画等、クレアでは全国の自治体や国際交流協会等の施策立案支援や人材育成、情報提供体制整備、NPO/NGO連携支援等を担当。法務省入管施設感染防止タスクフォース、在留支援のためのやさしい日本語ガイドラインに関する有識者会議等に携わる。
藤巻秀樹 Prof. FUJIMAKI Hideki
ジャーナリスト、北海道教育大学非常勤講師、筑波学院大学非常勤講師。専門は移民政策・多文化共生論。1979年東京大学文学部仏文科卒業、同年日本経済新聞社入社。大阪経済部、同社会部、パリ支局長、国際部次長などを経て編集委員。愛知県豊田市保見団地、東京・新大久保などの外国人集住地域に住み込み取材をして長期連載企画を執筆した。2014年~2020年、北海道教育大学国際地域学科教授。文部科学省「外国人児童生徒等の教育の充実に関する有識者会議」委員(2019年6月~2020年3月)。文部科学省「学校における外国人児童生徒等に対する教育支援に関する有識者会議」委員(2015年~2016年)。主要業績は、『「移民列島」ニッポン―多文化共生社会に生きる』(単著、藤原書店、2012年)、『開かれた移民社会へ』(共編著、藤原書店、2019年)、『「難民」をどう捉えるか―難民・強制移動研究の理論と方法』(共著、慶應義塾大学出版会、2019年)、『パリ同時多発テロとフランスの移民問題』(日仏政治研究第10号、2016年)、『多文化「共創」社会入門――移民・難民とともに暮らし、互いに学ぶ社会へ』(共著、慶應義塾大学出版会、2016年)、『日韓・日中関係悪化と在日韓国・中国人』(移民政策研究第7号、2015年)、『なぜ今、移民問題か』(共編著、藤原書店、2014年)など。
松本いく子 Ms. MATSUMOTO Ikuko

上智大学大学院実践宗教学研究科博士後期課程在籍。スタンフォード大学大学院教育学部国際開発教育研究科修士課程を経て、国際連合開発計画(UNDP)モザンビーク現地事務所及びジュネーブ支部に勤務し(1987-1994) 内戦下のモザンビークの社会・経済支援や停戦後の平和維持・選挙・民主化に向けた事業に従事。その後アジア開発銀行(ADB・マニラ本店1994-2016)にて、教育行政改革及び基礎教育・中等教育の拡充事業(フィリピン、インドネシア、ウズベキスタンなど)やADBの中長期戦略及び組織改革、東南アジア業務局及び太平洋島嶼業務局の教育・医療・社会福祉・公共政策支援に従事。2016年より大学院にて、「人」の命・心・尊厳・共存に焦点を置く諸宗教の活動を、「人」を資源・コストとみる開発援助とは異なる「もう一つの国際協働」の担い手として研究中。日本に生活する外国人と諸宗教の関わりにも関心を持つ。
「国際公務員の現場からー息の長い開発協力を目指して」『国際公務員になるには』横山和子著・編(ペリカン社、1996)“Is Religion Irrelevant to Development? Faith-based Initiatives and Development Discourses”( Sophia Journal of Asian, African, and Middle Eastern Studies/No.34, 2016)“Healing the Collective Grief: A Story of a Marshallese Pastor from Okinawa” Religions 2022, 13, 90.) 「忘れられた戦争の傷跡と修復−沖縄からマーシャル諸島に渡った具志忠太郎の軌跡から」『現代死生学』創刊号(2023)など。
山脇康嗣 Mr.YAMAWAKI Koji

さくら共同法律事務所パートナー弁護士
慶應義塾大学法学部法律学科卒業、慶應義塾大学大学院法務研究科修了
現在、慶應義塾大学大学院法務研究科非常勤講師(入管法担当)、慶應義塾大学大学院法務研究科グローバル法研究所(KEIGLAD)客員所員、第二東京弁護士会国際委員会副委員長、日本弁護士連合会人権擁護委員会特別委嘱委員(出入国在留管理庁との定期協議担当)、日本弁護士連合会多文化共生社会の実現に関するワーキンググループ委員を務める。
主著
『詳説 入管法と外国人労務管理・監査の実務〔第3版〕』(新日本法規、令和4年)―単著
『特定技能制度の実務』(日本加除出版、令和2年)―単著
『技能実習法の実務』(日本加除出版、平成29年)―単著
『入管法判例分析』(日本加除出版、平成25年)―単著
『Q&A外国人をめぐる法律相談』(新日本法規、平成24年)―編集代表・執筆
『外国人及び外国企業の税務の基礎—居住者・非居住者の税務と株式会社・合同会社・支店の税務における重要制度の趣旨からの解説—』(日本加除出版、平成27年)―共編著
『円滑に外国人材を受け入れるためのグローバルスタンダードと送出国法令の解説』(ぎょうせい、令和4年)―共著
『事例式民事渉外の実務』(新日本法規、平成14年)―分担執筆
『こんなときどうする外国人の入国・在留・雇用Q&A』(第一法規、平成4年)―分担執筆
「「特定技能2号」の対象分野拡大の意義と課題」季刊労働法283号
「技能実習制度及び特定技能制度の改革の方向性」日本労働法学会誌135号
「実務家からみた平成30年入管法改正に対する評価と今後の課題」季刊労働法265号
「入管法及び技能実習法の実務と今後の課題」季刊労働法262号
「一体的に進む外国人の受入基準緩和と管理強化」自由と正義2017年6月号
ラビ・マハルザン Prof. Dr. Ravi Maharjan
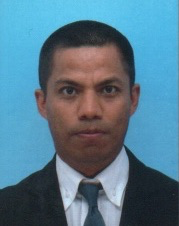
大東文化大学、麗澤大学、東京都立産業技術高等専門学校非常勤講師。博士(英語学)
専門分野:言語、異文化対立とアイデンティティ。現在はネパール人留学生の問題、在日ネパール人のアイデンティティ問題について研究を行っている。2009年に留学生として来日した以降、異文化理解交流、「もてなし英語」の教師、ネパール人コミュニティーに必要なとき通訳・翻訳ボランティアなどに参加。
主な業績に、“Multilingualism and Cultural Identity among Newari-Youth”, Multilingual Perspectives in Geolinguistics (2015), 190-197; “Challenges of Maintaining Linguistic Diversity and Ethnic Identity in Nepal”, Plurilingual Perspectives in Geolinguistics (2016), 109-113)など。
ダニエーレ・レスタ Prof. Dr. Daniele RESTA

イタリア・国立サレント大学大学院外国語外国文学研究科文芸・科学技術翻訳学専攻博士課程前期課程修了後、国費留学生として来日。大東文化大学大学院外国語学研究科日本言語文化学専攻博士後期課程修了、博士(日本言語文化学)。大東文化大学・国立音楽大学兼任講師。
専門は映像メディア論、比較文化学・比較文学、翻訳論。
主な業績に『いのちに国境はない―多文化「共創」の実践者たち』(共著、慶應義塾大学出版会、2017年)、“Transculturally Visualizing Tanizaki: Manji in Liliana Cavani’s Interno Berlinese” (Bunron 4、Heidelberg University – Japanologie)、“Migration, Gender and Multicultural Identity in Laura Bispuri’s Vergine Giurata”(『環境創造』第22号)その他。
山口美智子 Ms. YAMAGUCHI Michiko

米国コロンビア大学大学院社会福祉学部卒業
専門: 臨床ソーシャルワーク(ファミリー&チルドレン)
大学院時代のインターンシップ:
ニューヨークコーネル大学病院にて
HIV 外来クリニック、癌入院病棟、血友病患者の外来クリニックで臨床ソーシャルワーク、ケースマネッジメントを行う。
2年目はブロンクス地区の小学校で不登校ぎみの生徒の為のグループカンウセリングを担当する一方で同ブロンクス地区のコミュニティエージェンシーで児童虐待防止局のファンドで創られた家族維持プログラム(ファミリープリザベーションプログラム) のソーシャルワーカーとしてケースマネッジメント並びに個人、家族カウンセリングなどを行う。
2001年からは寮生の私立高校でスクールカウンセラーとして勤務
ニューヨーク市教育委員会の元で1年間アウトソースのセラピストとして心理的治療の必要な児童を家庭訪問し治療にあたる。
ニューヨーク市で作られた災害時の対応にあたる医療関係者からなるボランティアのリスポンスティーム、メディカルリザーブコープの一員